今回は“ee”を接尾辞に含む単語をまとめてみました。
語源から考えると、様々な単語を一気に本質理解することが出来ます。
一体どのようなものなのか? サクッと確認していきましょう!
※接尾辞とは、単語の末尾のつづりのことです。単語の品詞を大きく変える傾向があります。
“ee”を含む英単語まとめ
eeには、
- ee: ~される人/する人
というイメージがあることを意識してください。
「employee: 従業員、社員」は、
- employ: ~を雇用する
- ee: される人(⇒雇用される人)
というイメージです。
ちなみに、この逆が「employer: 雇用者、企業主」です。
- employ: ~を雇用する
- er: する人(⇒雇用する人)
※「er, or: ~する人」という接尾辞とが使われていますね。
そして、「ee: ~される人/する人」という接尾辞の単語を見る際は、下記の点に注目すると良いと思います。
- eeの部分にアクセントが置かれる
- 動詞の後ろにeeがくる時、「~される人」という意味になりやすい。
- 「ee: ~される人」という意味になっているとき、「er: ~する人」という語尾が付く単語が存在することが多い。つまり、「~する人」⇔「~される人」という対応関係が存在する際、erと区別するためにeeが「~される人」という意味で使われることが多い(例 「employee: 従業員」⇔「employer: 雇用者」)
「ee: ~される人/する人」というイメージを意識しつつ、下記の単語に目を通してみてくださいね。
ポイント
<~される人>
- addressee: 受取人(「address: ~に宛先を書く」)
- appointee: 任命された人(「appoint: ~を任命する」)
- awardee: 受賞者(「award: ~を授与する、贈る」)
- conferee: ①(学位などの)受領者(⇔「confer: 相談する、協議する」、「conferrer: 授与者」)、②相談相手、会議出席者
- consignee: 荷受人、販売受託人(「consign: ~をゆだねる、捨てる」⇔「consignor: 受託者、荷送人」)
- donee: 被援助者(「donate: ~を寄付する」⇔「donor: 寄付をする人、提供者、ドナー」)
- employee: 従業員、社員(「employ: ~を雇用する」⇔「employer: 雇用者」)
- examinee: 受験者(「examine: ~を調査する、検査する」⇔「examiner: 試験官、検査官」)
- mortgagee: 抵当権者(「mortgage: ~を抵当に入れる、担保にする」⇔「mortgagor: 抵当権設定者」)
- nominee: 指名された人、名義人(「nominate: ~を推薦する」⇔「nominator: 指名者」)
- payee: (金銭の)受取人、被支払人(「pay: ~を支払う」⇔「payer: 支払人」)
- trainee: 訓練を受ける人、研修生(「train: ~を訓練する」⇔「trainer: トレーナー、調教師」)
- vendee: 買い手、買い主(「vend: ~を販売する、売る」⇔「vendor: 売主、販売業者」)
<~する人>
- absentee: 欠席者、欠勤者(「absent: 欠席している」)
- attendee: 出席者、参加者(「attend: ~に参加する」)
- devotee: 愛好者、信者(「devote: ~を捧げる」)
- refugee: 難民、避難者(「refuge: 避難、保護」)
- retiree: 定年退職者(「retire: 退職する」)
- returnee: 帰国子女、帰国者、帰還者(「return: 戻る」、「returner: 戻ってきた人、職場復帰した人」)
おわりに
いかがでしたか? 語源は威力抜群なので、超オススメの単語勉強法です。たくさんの文章を読み込むのと並行で、語源学習も出来ると効果抜群だと思います。

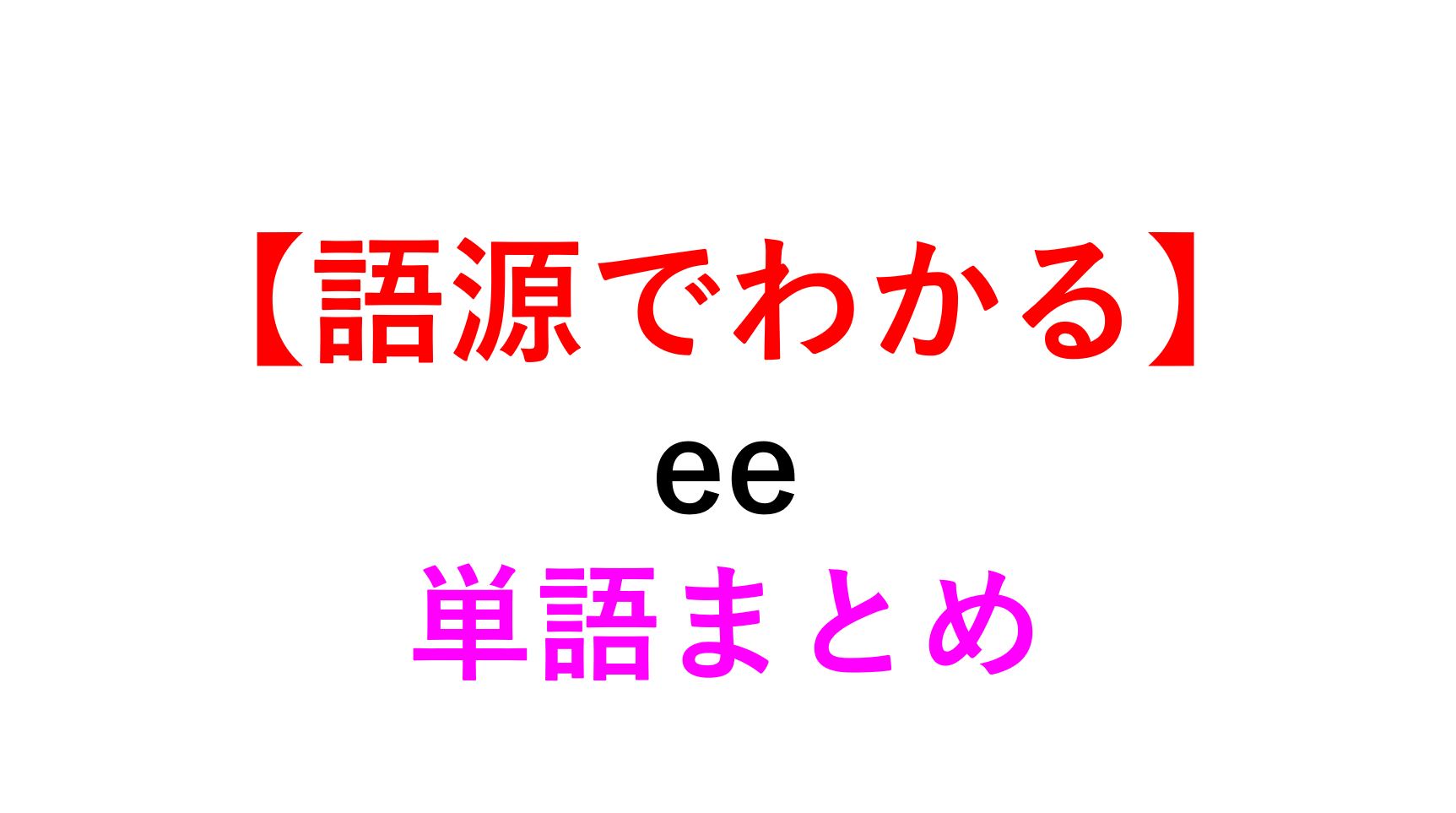
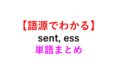
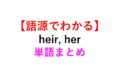
コメント