こんにちは、今回はちょっと小話です。
「長い単語にはmore/mostを付ける!」とは中学校で習うルールですが、なぜそのようなルールが生まれたのか、考えたことはありますか?
実は一応それらしい理由があるので、今回はそれを紹介したいと思います。
ちなみに、これを知ってもテストの点は上がりません。笑
完全に趣味の世界の話です。
more/mostはフランス語からの流入で生まれた
もともと古英語(大昔の英語)では、比較級と最上級は-er/estで表現していました。
しかし、ノルマン (フランス語圏の人々)がイギリスを支配したことで、フランス語が英語に一気に流入したのですね。
その時に使われるようになったのがmore/mostです。
フランス語では、
- more = plus
- the most = le/la/les plus
ですが、それが英語にも入ってきたのです。
もちろん、この時代に入ってきたのはそれだけではありません。
実に大量の言葉が入ってきました。ノルマンはイギリスを支配したので、堅い言葉 (≒ちょっとエラそうな言葉)は、特にフランスの流入が顕著にみられました。
で、そういった語の特徴として、通常の英語よりも綴りが長いのです。
- attorney: 弁護士
- defendant: 被告人
- retreat: 退却
- commence: 開始する
- purchase: 購入する
- encounter: 遭遇する
- beautiful: 美しい
- diligent: 勤勉な
- honorable: 尊敬すべき
等々…
はじめのうち、more/mostはフランス語語源の言葉と結びついて使われていましたが、
その後、
- 長い言葉はmore/most
- 短い言葉は-er/-est
というルールが確立することになりました。
なぜ単語の長さでmore/mostを使用するかどうかが決まったか?
…そうです、フランス語よりも、英語のつづりの方が長い傾向があったからです。
その結果、英語に語源を持つものでも、長ければmore/mostと結びつくという流れが出来たようです。

なるほどね!
おわりに
いかがでしたか?
特になくても困らない知識ですが、こういった背景を知っていると、なんだか世界が広がって感じますよね。単なるコミュニケーションの道具でしかない英語が、歴史と奥行きを持った存在に感じられます。
英語って結構面白いな、と思ってもらえたのなら幸いです。

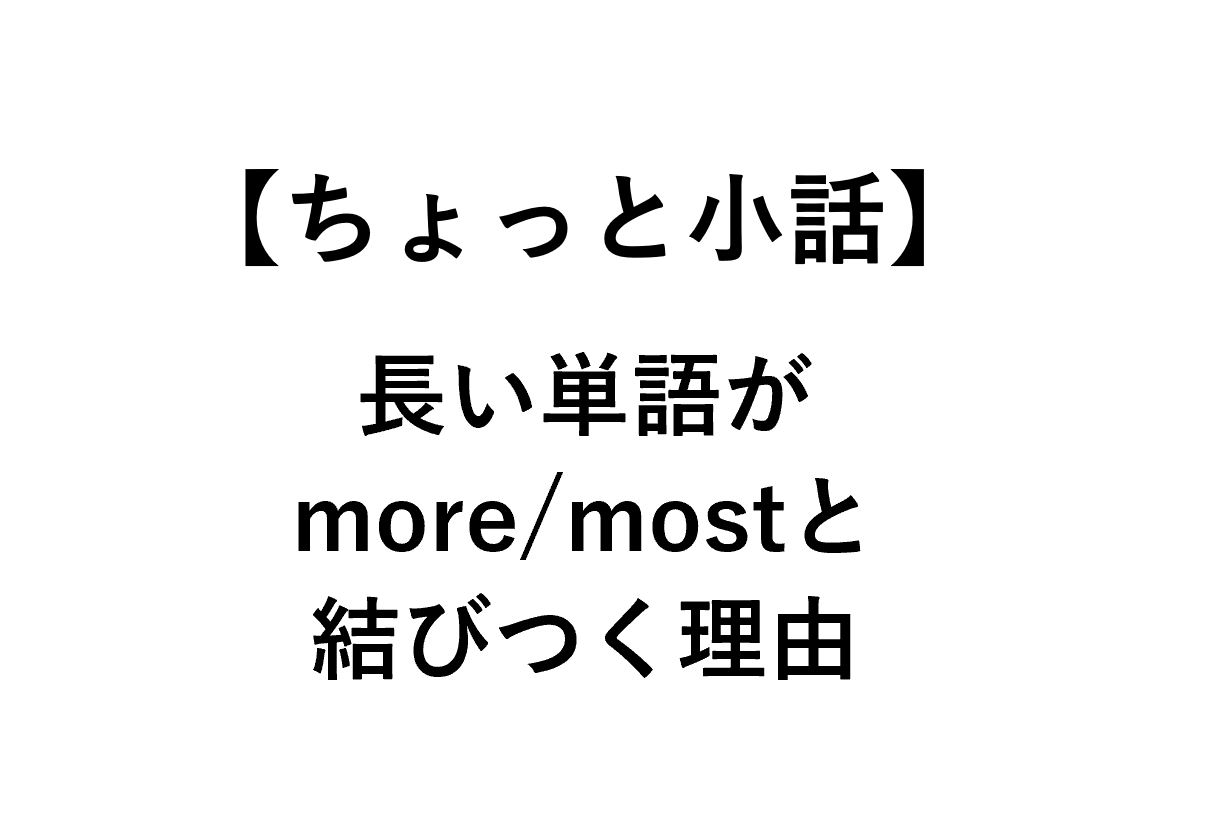
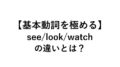
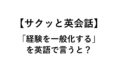
コメント