今回はargue/quarrel/dispute/debate/discuss「議論する」の意味・用法の違いについてまとめてみたいと思います。
一見似ている単語ですが、その中身は結構違います!
今回はその内容を徹底的にわかりやすく説明してみます。
argue/quarrel/dispute/debate/discuss「議論する」の意味・用法の違い
まずはargue/quarrel/dispute/debate/discuss「議論する」の意味・用法の違いのまとめから。それぞれ下記のような違いがあります。
- argue: 議論・口論する(強く主張 / 感情的)
- quarrel: 口げんかする (argueより感情的)
- dispute: ~を議論する、~に強く反論する(激しくぶつけ合う / 感情的)
- debate: ~を討論する(ルールに従い、各陣営に分かれる)
- discuss: ~について議論する(問題解決のため話し合う)
ざっくりと、
- argue/quarrel/dispute ⇒感情的な表現
- debate/discuss ⇒感情的な意味合いは薄い表現
というグループに分けられます。
下記にて具体的に見ていきましょう!
argue/quarrel/dispute/debate/discuss「議論する」の例文
以下が例文です。
argue/quarrel/dispute
まずはargue/quarrel/disputeです。
どれも、感情的に議論するという意味合いが強い単語です。
それぞれの細かい違いは下記の通りです。
- argue: 議論・口論する(強く主張 / 感情的)
- quarrel: 口げんかする (argueより感情的)
- dispute: ~を議論する、~に強く反論する(激しくぶつけ合う / 感情的)
argueは自分の意見を強く主張するイメージで、
quarrelはそれをさらに強い意味にしたイメージです。
(「quarrel: 喧嘩」という名詞の意味もありますね)
disputeは意見をぶつけ合ったり、相手に激しく反論するイメージです。
(「dis: 反対の」という意味があるのです)
上記のイメージを頭に入れつつ、下記の例文をチェックしていきましょう。
We argued about the social problem.
We quarreled about the social problem.
We disputed the social problem.
(私たちは社会問題について議論した)
なお、上記の例文を見てもわかる通り、disputeは他動詞なので、aboutは不要です。
debate/discuss
次にdebate/discussです。
どちらも感情的な意味合いは薄いです。むしろ、頭を冷静にして、客観的に議論するイメージが強い単語です。
両者には下記のような違いがあります。
- debate: ~を討論する(ルールに従い、各陣営に分かれる)
- discuss: ~について議論する(問題解決のため話し合う)
debateについては、「ディべート大会」という表現が日本語にも溶け込んでいますね。二つの陣営(ある問題に対するYes/Noの立場)に分かれ、ルールに従い討論しあうイメージの単語です。
discussも、「ディスカッションをする」という表現が日本語に溶け込んでいます。問題を解決するため、感情的ではなく議論をするイメージです。
それぞれの例文はコチラです。
We debated the issue.
We discussed the issue.
(わたしたちはその問題について討論/議論した)
先ほど出てきたdispute同様、debate/discussも他動詞なのでaboutが不要な点にも要注目です。
まとめ
いかがでしたか? 最後に改めてまとめです。
- argue: 議論・口論する(強く主張 / 感情的)
- quarrel: 口げんかする (argueより感情的)
- dispute: ~を議論する、~に強く反論する(激しくぶつけ合う / 感情的)
- debate: ~を討論する(ルールに従い、各陣営に分かれる)
- discuss: ~について議論する(問題解決のため話し合う)
表面的な和訳だけではなく、イメージで捉えられるといいですね。


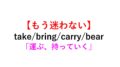
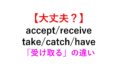
コメント