今日はnot~until…を説明したいと思います。
コレ、言い換えも含めてなかなか厄介な表現なんですね。
厄介なので、試験にも出やすい。
ただ、死ぬほどわかりやすく解説するので、これを機会に得点源にしてしまいましょう!
S not ~ V until~の意味/用法まとめ -強調構文/倒置への書き換え
まずはS not V until~の意味と用法をまとめてみたいと思います。強調構文/倒置への書き換えもまとめてあります。
- S not V until~ : ~までSVしない、~してはじめてSVする

よくわからない…
それぞれを例文付きで詳しく見ていきましょう!
S not ~ V until~の例文
S not ~ V until~の例文はこちらです。
S not V until…
まずは「S not V until… : …まで SVしない、…してはじめてSVする」です。

どうしてこんな訳になるの?
具体的な例文と一緒に考えてみましょう。
He did not know the fact until he was twelve.
(彼は12歳になるまでずっと、その事実を知らなかった
= 彼は12歳になってはじめて、その事実を知った)
until…が「…までずっと」という訳を持つのがポイントです。
図で示すと下記のようなイメージになります。
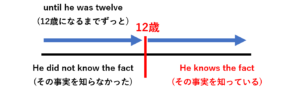
「12歳になるまでずーっと、その事実を知らなかった」は、
「12歳以降はその事実を知っていた」というコトになりますよね。
それを自然な日本語にすると、「12歳になってはじめて、その事実を知った」となるわけです。
It is not… that SV
次に「It is not… that SV: …してはじめてSVする」です。これは強調構文が使用されています。
端的に言うと、強調したい部分をIt is~that…の”~”部分に挟み込む表現です。作り方は下記の通りです。
- 元になる文を用意する。(We want to visit New York.)
- 強調したい部分を”It is XX that~”とIt isとthatの間に挟み込み、残りをそのまま後ろへ持ってくる。(It is New York that we want to visit.)
※参考記事:【サクッと理解】強調構文のitとは?
今回は、
He did not know the fact until he was twelve.
の下線部分をIt is~that…で挟んでいます。
残りの部分は、ほぼそのまま”…”部分に書かれている点も意識してくださいね。
It was not until he was twelve that he knew the fact.
(彼は12歳になってはじめて、その事実を知った)
なお、notの部分が挟まれている理由は、英語が早めにyes/noをはっきりさせたがる言語だからです。
後ろにnotを残し”It was until he was ten that he did not know the fact.”としてしまうと、文の後半で意味が真逆にひっくり返ってしまいます。そのため、notをuntilのカタマリと一緒に、文の最初の方に持ってきているのです。
Not until… VS
最後に「Not until… VS: …してはじめてSVする」です。
Not until…を、否定的な意味のカタマリとして考えてください。
否定的な意味のカタマリが文頭にくるとき、後ろの語順は倒置する(SV⇒VSになる)のです。
※参考:【倒置全9パターン】英語で倒置が起こる場合をまとめてみた
例文はコチラ。”did(S) he(V)”という語順に注目です。
Not only he was twelve did he know the fact.
(彼は12歳になってはじめて、その事実を知った)
まとめ
いかがでしたか?
最後に書き換えパターンと例文を改めてまとめてみましょう。
- S not V until~ : ~までSVしない、~してはじめてSVする
He did not know the fact until he was twelve.
= It was not until he was twelve that he knew the fact.
= Not until he was twelve did he know the fact.
(彼は12歳になってはじめて、その事実を知った)
理解をしたら、あとは何度も音読をして、身体で覚えてくださいね!

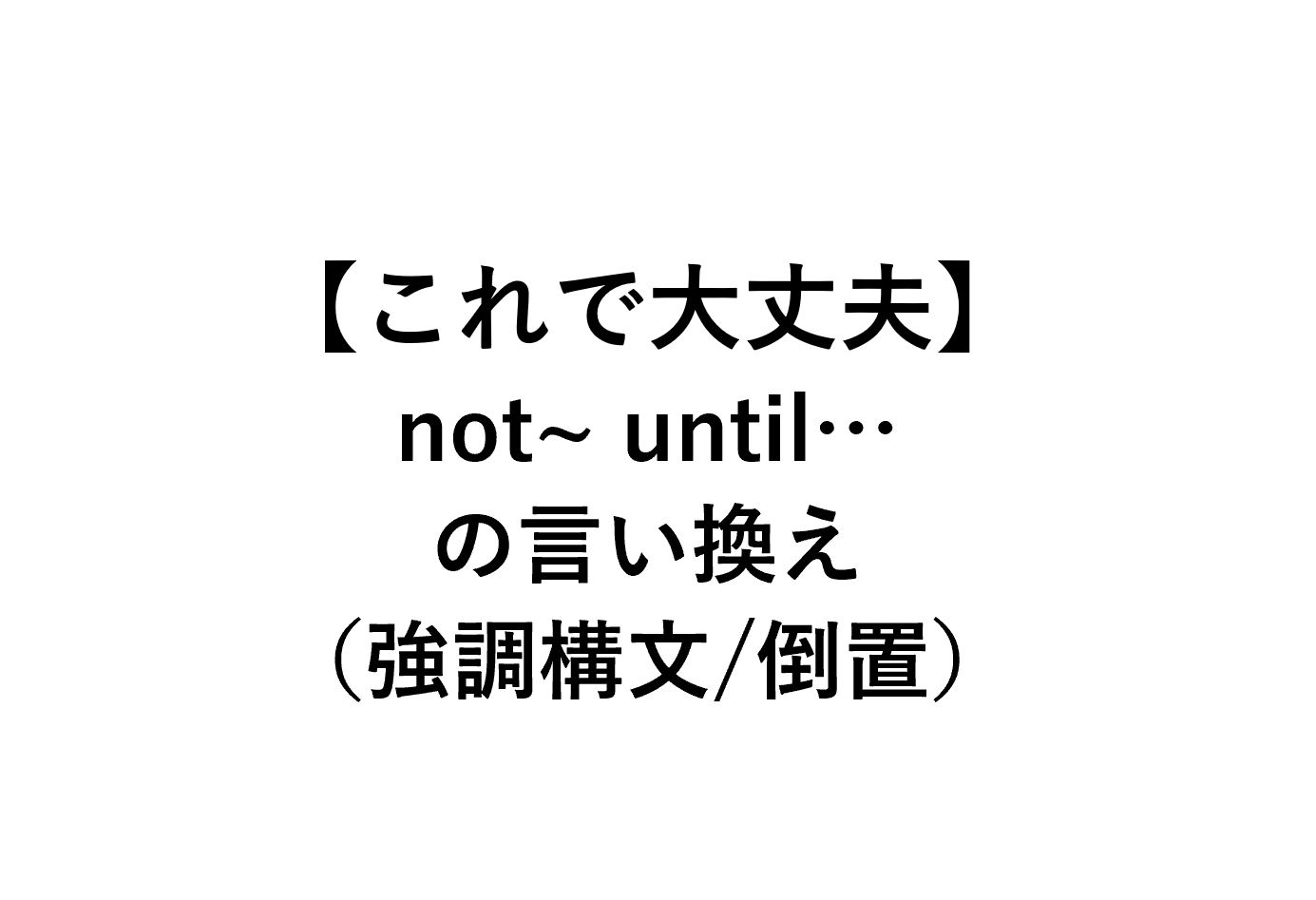
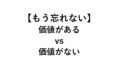

コメント