今回はthat S should 原形の動詞/形容詞をまとめたいと思います。

なにそれ?
時制や人称に関係なく、that内が強制的に(should) 原形の形をとってしまう動詞のコトです。

ワケわからん…
パターンは決まっているので、この際だから一気に覚えてしまいましょう。そして、「なぜそうなるのか?」という理由も一緒に説明したいと思います!
【仮定法現在】that S should 原形の動詞/形容詞まとめ
まずは、that S should 原形の動詞/形容詞の代表例を示しましょう。
<仮定法現在に共通するポイント>
- 「まだ現実になっていない」事柄について使用される
<動詞>
- 提案:suggest 提案する*、propose 提案する、recommend 勧める、advise 助言する
- 命令/要求:demand 要求する、ask 要求する、insist 要求する*、request 要請する、require 求める、desire 強く望む、order 命令する、urge 強く言い張る
- 決定:decide 決める、determine 決める
* 「suggest: 示唆する」、「insist: 主張する」の意味の時は、仮定法現在にはならない
<形容詞>
- 提案:advisable/desirable 望ましい、crucial きわめて重要な、expedient 得策な、imperative 絶対必要な、important 重要な*、necessary 必要な、urgent 緊急の、vital 極めて重要な
- 命令/要求:essential 不可欠な
* 「important: 重要な」は、話し手がそれを事実と考えていれば、仮定法現在が使用されないこともある
demand(~を要求する)という単語を例に説明します。
例文はコチラ。
He demanded that she should tell him the truth.
= He demanded that she tell him the truth.
(彼は、彼女が彼に真実を話すことを要求した)
特に下の方の例文を見てください。この例文を見て、何か違和感を覚えないでしょうか?

…あ、that節内の動詞がおかしい
そうですね、that節内の動詞の形がおかしいです。
that節の外では、demandedという過去形が使われています。とすれば、普通はthat節の中でも過去形が使われるハズなんです。
ただ実際は、
- that she tell him the truth
のように、現在形が平然と使われているんです。
しかも、主語がsheなのに、tellsではなくtellが使われているんです。これって、普通であればめちゃくちゃおかしいことなんです。
ただ、実はコレ、demandが特殊な動詞だから動詞の原形が使われているのです。
demand等のような特定の動詞や形容詞(先ほど一覧でまとめた単語です)が使われると、that節の中はshould 原形か、原形(三人称単数のsもついていない動詞の元の形)を使う必要があるのですね。

どうしてそんなことをする必要があるの?
その理由は、次で説明します。
shouldや原形が使われる理由
仮定法現在でshouldや原形が使われるのはなぜなのでしょう?
先ほどの例文を改めてみてみましょう。特に下の方の例文に注目です。
He demanded that she should tell him the truth.
= He demanded that she tell him the truth.
(彼は、彼女が彼に真実を話すことを要求した)
「彼が要求した」「彼女が彼に真実を話すことを」という意味の文ですね。
「要求」の内容、つまりは「彼女が彼に真実を話すこと」は要求した時点で現実になっているでしょうか?
答えはNOですね。「彼女が彼に真実を話すこと」がまだ現実になっていない、真実をまだ話してもらっていないからこそ、そうすることを要求しているわけです。つまり、要求の内容であるthat節の「彼女が彼に真実を話すこと」は、まだ現実になっていない出来事なのです。
このように、
- 「頭の中にあるだけで、事実になっていないコト」
- 「まだ実現しておらず、これから行動を起こすコト」
に対して、原形を使うことで、「まだ現実になっていない感」を表現しているのです。

原形が「まだ現実になっていない感」を持つ…?
実は、命令文にも同じ感覚があるとされています。例えば、下記の例文を見てください。
Tell him the truth.
(彼に真実を話しなさい)
「真実を話せ」とわざわざ命令しているのですから、その命令の内容はまだ現実になっていないはずですよね。現実になっていないからこそ、命令しているわけです。
このようにして考えると、仮定法現在が使われる動詞/形容詞が、全て「これから○○することを要求する/命令する/提案する…」といった意味合いを帯びていることに気が付くはずです。
<仮定法現在に共通するポイント>
- 「まだ現実になっていない」事柄について使用される
<動詞>
- 提案:suggest 提案する*、propose 提案する、recommend 勧める、advise 助言する
- 命令/要求:demand 要求する、ask 要求する、insist 要求する*、request 要請する、require 求める、desire 強く望む、order 命令する、urge 強く言い張る
- 決定:decide 決める、determine 決める
* 「suggest: 示唆する」、「insist: 主張する」の意味の時は、仮定法現在にはならない
<形容詞>
- 提案:advisable/desirable 望ましい、crucial きわめて重要な、expedient 得策な、imperative 絶対必要な、important 重要な*、necessary 必要な、urgent 緊急の、vital 極めて重要な
- 命令/要求:essential 不可欠な
* 「important: 重要な」は、話し手がそれを事実と考えていれば、仮定法現在が使用されないこともある
なお、ただ単に原形不定詞を使うだけだと、”she tell him the truth”のように、sheが主語なのに三単現のsが付かないケースも出てきてしまいます。
仮定法現在の文法としては正しいんですが、なんとなく気持ち悪いですね。
そして、その感覚はネイティブたちも同じだったようです。その気持ち悪さを解消するため、should doという形が誕生したのですね。shouldを挟んでおけば、後ろに動詞の原形がきても違和感ありませんから。
このような背景があり、仮定法現在ではshould 原形 / 原形が使われるようになったのです。
※なお、アメリカ英語では原形、イギリス英語ではshould 原形を使うのが一般的のようです。
例文
上記を理解したところで、例文をいくつかご紹介します。
that節の中がshould 原形 / 原形の形をとっていることに注目してください。
提案
suggestを例に考えてみましょう。
He suggested that the meeting be postponed until Wednesday.
= He suggested that the meeting should be postponed until Wednesday.
(彼は、ミーティングを水曜まで延期してはどうかと提案した)
be postponedで「延期される」ですがポイントです。普通はbeの部分が主語や時制に応じて変化するのですが(is、was、will beなど)、今回はsuggestが使われているので、be/should beが続いています。
また、形容詞でも同様のことが起こります。
It is advisable that he go there by car.
= It is advisable that he should go there by car.
(彼はそこへタクシーで行くのが望ましい)
要求
demandを例文に考えてみましょう。
She demanded that John earn ten million yen a year.
= She demanded that John should earn ten million yen a year.
(彼女は、ジョンが毎年1,000万円稼ぐことを要求した)
earnで「~を稼ぐ」ですね。earnの原形/should earnが使われている点に注目です。
決定
decideを例文に考えてみましょう。
They decided that they start the plan.
= They decided that they should start the plan.
(彼らは、彼らがその計画を開始することを決定した)
startで「~を始める」ですね。
これまでと同じように、時制の一致でstartedとはならず、startの原形/should startが使われている点に注目です。
suggestなのに原形にならない⁈
これまでは、should 原形や原形が使われるパターンを見てきました。いわゆる、仮定法現在が使われるパターンですね。

suggestとか、特定の動詞が使われていれば仮定法現在になるんだよね
基本はそうですが、100%ではないという点に注意してください。
たとえば次の例文では、仮定法現在が使われていません。
The survey results suggest that the economy is improving.
(その調査の結果は、経済が良くなっていることを示唆している)
suggestが使われているにもかかわらず、that内はisが使われています。beやshould beの形になっていません。

どうして???
なぜなら、suggestは「示唆する」という意味で使われているからです。
仮定法現在が使われるのは、「提案」「要求」「決定」という意味のときでした。
これらの意味のとき、仮定法現在が使われるのは、まだ実現していない感を出すためでしたね。
一方、「示唆する」という意味のsuggestは、「まだ実現していないんですよ!」というニュアンスが薄れていますね。示唆される内容が、既に現実の事実として存在する可能性を意味しているわけです。そのため、「示唆する」の意味で使用された場合は、that内の動詞は仮定法現在の形にはならないのです。
同じようにinsistも、「(事実に基づき)主張する」という意味合いで使われたときは、仮定法現在のルールが適用されません。
事実に基づき主張しているということは、「まだ実現していないんですよ!」というニュアンスがないわけです。やはり、話し手にとっては、「これは事実なのだ!」という気持ちが強いのですね。
他にも、形容詞のimportantは「重要だ」という意味でも、話し手の意識が「実現してない! / これは事実だ!」のどちらに向いているかで、仮定法現在が使われる / 使われないこともあります。
仮定法現在で大切なのは、「まだ実現していない感」なのですね。

機械的に判断するだけだと、間違えるってコトだね!
おわりに
いかがでしたか? この分野は最初は面食らいので、苦手とする受験生も多いです。
ただ、「提案」「決定」「要求」で仮定法現在が使われる理由を考えてみると、理解がぐっと進むハズです。

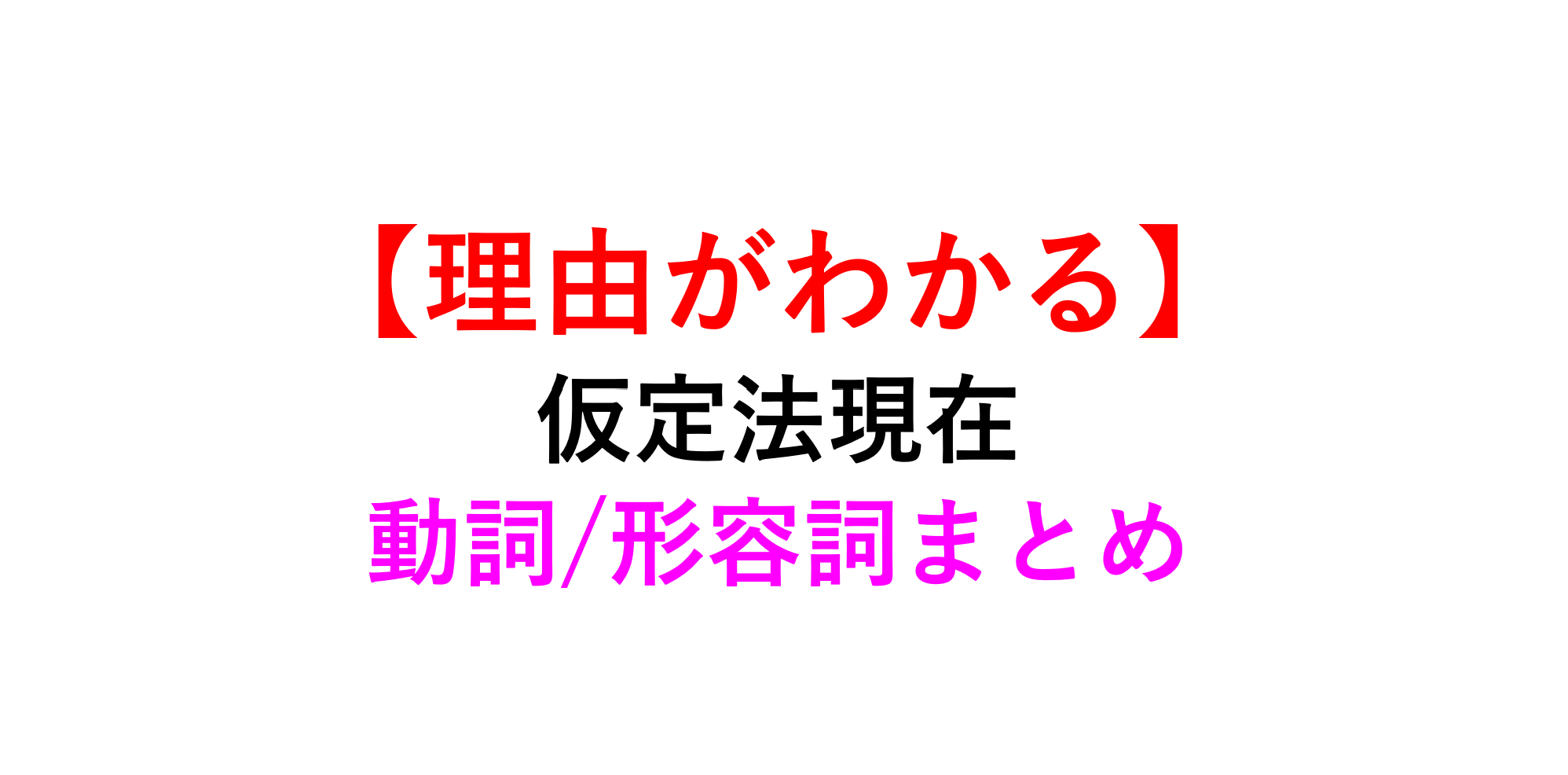


コメント
SV that S’ should V’ … の形でSが無生物、Vがpredictのような推測系の動詞だった場合は「…S’がV’するはずだと予測する」と、予測のshouldになるのでしょうか。
ご質問とは少しずれるかもしれませんが、たとえばstrangeなどの形容詞が使われた場合、驚きの意味を込めてshouldが使われることもあります。これは仮定法現在とは異なる意味合いで使われています(書き換える場合、直説法を使うことになります)。
It is strange that she should agree(agrees) with the his proposal.