今回扱うのは現在分詞と過去分詞です。ややこしく、受験生泣かせの分野です。

違いがよくわからない…
大丈夫、今回も死ぬほどわかりやすく説明します。
この記事を読むと、
- 現在分詞と過去分詞の違いや使い分け
- 現在分詞と過去分詞の主な使い方
が理解できますよ。
では、始めましょう!
そもそも分詞って?
分詞とは、動詞をVing / Vp.p.にしたもののことを言います。
たとえば、surpriseは「驚かせる」という意味の動詞ですね。これがsurprising/surprisedと形を変えれば分詞になったといえます。
では、surprising/surprisedで何が違うのか?
下記で見ていきましょう。
現在分詞と過去分詞の意味/用法の違い
現在分詞と過去分詞の意味/用法の違いは下記のとおりです。
- Ving (surprising)が現在分詞で、「Vさせるような (驚かせるような)」
- Vp.p. (surprised)が過去分詞で、「Vされるような (驚かされるような)」
という訳になります。
ポイントは訳の違いです。
現在分詞は「Vさせるような」というように、能動態の訳になっています。
一方、過去分詞は「Vされるような」というように、受動態の訳になっています。
例文で見てみましょう。
He was surprising.
(彼は驚かせるような人だった)
He was surprised.
(彼は驚かされた)
上の例文はVingの形なので、「彼は→驚かせるような」という訳になります。「驚かせる」という訳からもわかる通り、周囲の人を驚かせているわけですね。だから「驚かせるような人」という訳になっています。
一方、下の例文はVp.p.の形なので、「彼は←驚かされた」という訳になります。「驚かされた」という訳からもわかる通り、驚いているのは彼自身です。だから「彼は驚かされた」という訳になっています。
現在分詞と過去分詞の違いは、「Vしている」のか「Vされている」のかという点です。
- 現在分詞:Vingの形 /「Vしている、Vするような」という訳
- 過去分詞:Vp.p.の形 /「Vされる、Vしてしまった」という訳
※過去分詞の「Vしてしまった」は完了形の訳です。Vp.p.って完了形の形でもありますからね。ただ、今回コチラの訳は取り上げないので、軽く流してOKです
現在分詞と過去分詞の使い方
基本を押さえたところで、現在分詞と過去分詞の使い方の違いをもう少し具体的に見ていきます。いくつかパターンがあるので、それを順番に押さえていきましょう。
パターンは、
- 形容詞として名詞を修飾
- SVC構文
- SVOC構文
- 付帯状況with X Y
です。
形容詞として名詞を修飾
形容詞として名詞を修飾するパターンです。これが一番メジャーですね。
例文で見てみましょう。
He told me surprising news.
(彼は私に驚くようなニュースを言った)
English is a language spoken all over the world.
(英語は世界中で話されている言語です)
赤字部分が分詞、太字部分が修飾される名詞です。
上は現在分詞で、「驚くような→ニュース」、下は過去分詞で「言語←世界中で話されている」というように修飾関係が成り立っています。
注目してほしいのは、下の方の例文で、過去分詞が後ろから修飾しているところです。これ、過去分詞だから後ろから修飾しているわけじゃないんです。2語以上のカタマリとなっている場合、後ろから修飾するのです。
原則として、分詞のカタマリが1語なら前から修飾、2語以上なら後ろから修飾します。ちなみにこれは、分詞のみならず、フツーに形容詞を使うときにも適用されるルールです。
- 1語なら名詞の前
- 2語以上なら名詞の後ろ
SVC構文
SVC構文のC部分に現在分詞、過去分詞がくることもあります。
こちらが例文です。実は、一番初めに挙げたのと同じものです。
He was surprising.
(彼は驚かせるような人だった)
He was surprised.
(彼は驚かされた)
SVCのCの部分に現在分詞、過去分詞がそれぞれきています。
SVOC構文
動詞によってはSVOCの形をとるものがあります。たとえば、”keep O C: OをCのままにしておく”なんかが有名ですね。
例文で見てみましょう。
He kept me waiting.
(彼はわたしを待たせたままにした)
He kept the door locked.
(彼はドアを閉めたままにした)
日本語訳だけだとわかりづらいですが、上が現在分詞、下が過去分詞です。上の文で過去分詞を使うことはできないし、下の文で現在分詞を使うことはできません。

どうしてだろう
OとCの関係に注目です。
上の文は、O=me, C=waitingです。このとき「わたしが」「待っている」という関係が成り立っていますね。特に受動態の関係ではないので、現在分詞を使っています。
一方の下の文は、O=the door, C=lockedです。このとき「ドアが」「閉じられている」という関係が成り立っていますね。Oが「~されている」というように、受動態の関係があるので、過去分詞を使っています。
Oが「している」のか「されている」のかで現在分詞、過去分詞が決まってきます。最初に触れた基本事項と同じです。日本語で考えるのではなく、「OとCの間に受動関係があるかどうか?」で考えるのがポイントです。
- OがCしている:現在分詞
- OがCされている:過去分詞
ちなみに、SVOCを取る動詞に知覚動詞や使役動詞というものがあります。こちらについては下記の記事をお読みくださいね。超重要事項ですが、5分程度でサクッと読めますよ。
知覚/使役動詞の意味と用法 -原形不定詞/現在分詞/過去分詞の違い
付帯状況with X Y
付帯状況with X Yです。
まずは例文を見てみましょう。
I cannot watch TV with you standing there.
(君がそこに立っていて、わたしはテレビを観ることができない)
まず、文の頭で「わたしはテレビを観ることができない」と言っていますね。これが文の核、中心となる部分です。withはそこへ追加説明を付け足すイメージです。
withで「~と一緒に」という訳は聞いたことがあると思いますが、withって付け足すイメージなんです。
で、with以下を見てみると、“X = you”, “Y = standing there”です。X, Y部分を直訳すると「君がそこに立っている」です。withがあるので、「君がそこに立っている」という訳を文の核にぺたっとくっつけます。
その結果、「君がそこに立っていて、わたしはテレビを観られない」という訳になるのです。
鋭い方はお気づきでしょうが、XとYの間に受動態の関係が成り立っていれば、Y部分には過去分詞が使われます。
He sat in the chair with his arms folded.
(彼は、彼の腕を組んで、椅子に座っていた)
“X = his arms”, “Y = folded”の間には「腕が」「組まれる」というように、受動態の関係が成り立っていますね。
- XがYしている:現在分詞
- XがYされている:過去分詞
※動作の主体が「文の主語≠X Y」のとき、with X Y構文が使われます。「文の主語=X Y」のときはこの構文を使用せず、単純にVingの分詞構文を使ってしまいます
おわりに
いかがでしたか?
現在分詞、過去分詞のどちらを使うべきかは、最初のうちは見極めが難しいかもしれません。最低限のルールを理解したら、あとは問題をたくさん解いて、身体で覚えてしまいましょう。
ポイントは、日本語訳で考えるのではなく、「受動態の関係かどうか」を意味内容から考えることです。

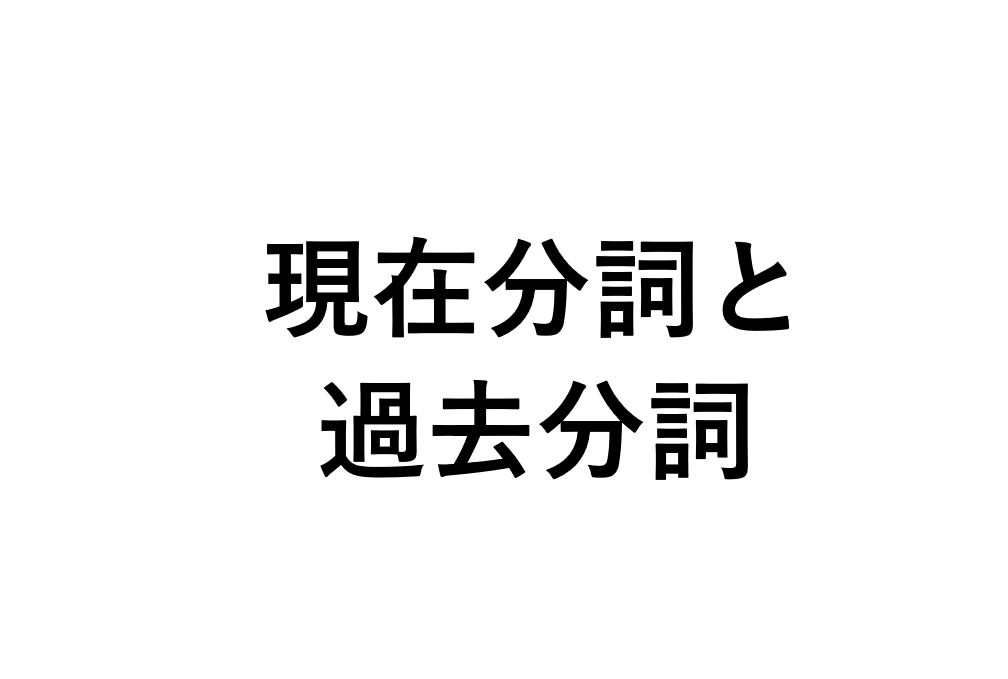
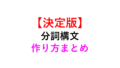

コメント