今回は不定詞の否定についてお話ししたいと思います。
不定詞の中でも特に、副詞用法の目的の否定です。

なに言ってるかわからない!
そんな方も大丈夫。死ぬほどわかりやすく説明します。
なお、不定詞については、ここら辺の過去記事も参考になるかもしれません。
不定詞の否定形の作り方
まずは、不定詞の否定形の作り方を確認しておきましょう。
これは超簡単。to Vの直前にnotを付けるだけです。
よほどのことがない限り、to Vの直前にnotを付ければ否定形の完成です。
これは、不定詞には全て共通のルールです。
名詞用法、形容詞用法、副詞用法…不定詞には様々な用法がありますが、どの用法だろうと、to Vの直前にnotというルールは同じです。to not Vとなることもありますが、まずはnot to Vが基本だと押さえておきましょう。
註:形容詞用法や副詞用法でnot to Vの形ってあまり見ない気がします。自分で書いていて気がつきました。
例えば、名詞用法でのnot to Vは次のような感じです。
not to Vで「Vしないこと」というカタマリを作っています。
名詞用法:I decided not to visit his house. (私は、彼の家を訪れないことを決めた)
副詞用法の目的での否定「Vしないように」は使えない?!
さて、not to Vで不定詞の否定が作れることを確認したら、副詞用法の目的での否定について考えてみましょう。

そもそも、副詞用法の目的ってなに??
副詞用法の目的とは、「Vするために」と訳すパターンのことです。to Vのほか、in order to V, so as to Vを使っても同じような意味に出来ます。
例文はコチラ。
I went there to see him.
= I went there in order to see him.
= I went there so as to see him.
(私は、彼に会うためにそこへ行った)
さて、これを「Vしないために、Vしないように」という否定の意味にしたいとき、どうすればよいでしょうか?

not to Vにすればいい!
おしいです!
実は、副詞用法の目的を否定の意味にするときは、not to Vとはせず、in order not to V, so as not to Vの形を使うのが一般的なのです。「Vしないために、Vしないように」の意味については、not to Vで表現することが出来ないのですね。
例文はコチラです。
I went there not to see him.= I went there in order not to see him.
= I went there so as not to see him.
(私は、彼に会わないように (= 会わないために)そこへ行った)
例外
ただ、何事にも例外はあります。
副詞の目的の否定でも、
- take care:世話をする、気を配る
- be careful:気を付ける
- not to talk but to act: 話すためではなく、行動するために
では、not to Vを使うことが一般的です。
例文で見てみましょう。
Take care not to break the eggs.
(その卵を割らないよう注意してね)
Be careful not to catch a cold.
(風邪を引かないよう気をつけて)
We are here not to talk but to act.
(我々は話すためではなく、行動するためにここにいるのだ)

2つだけなら覚えるのもカンタンだね!
意味も似ているし!
おわりに
いかがでしたか?
今回は細かい内容でしたが、覚えておけば、英作文や英会話で結構使える知識です。一個ずつ、丁寧に知識を積み重ねていきましょう!

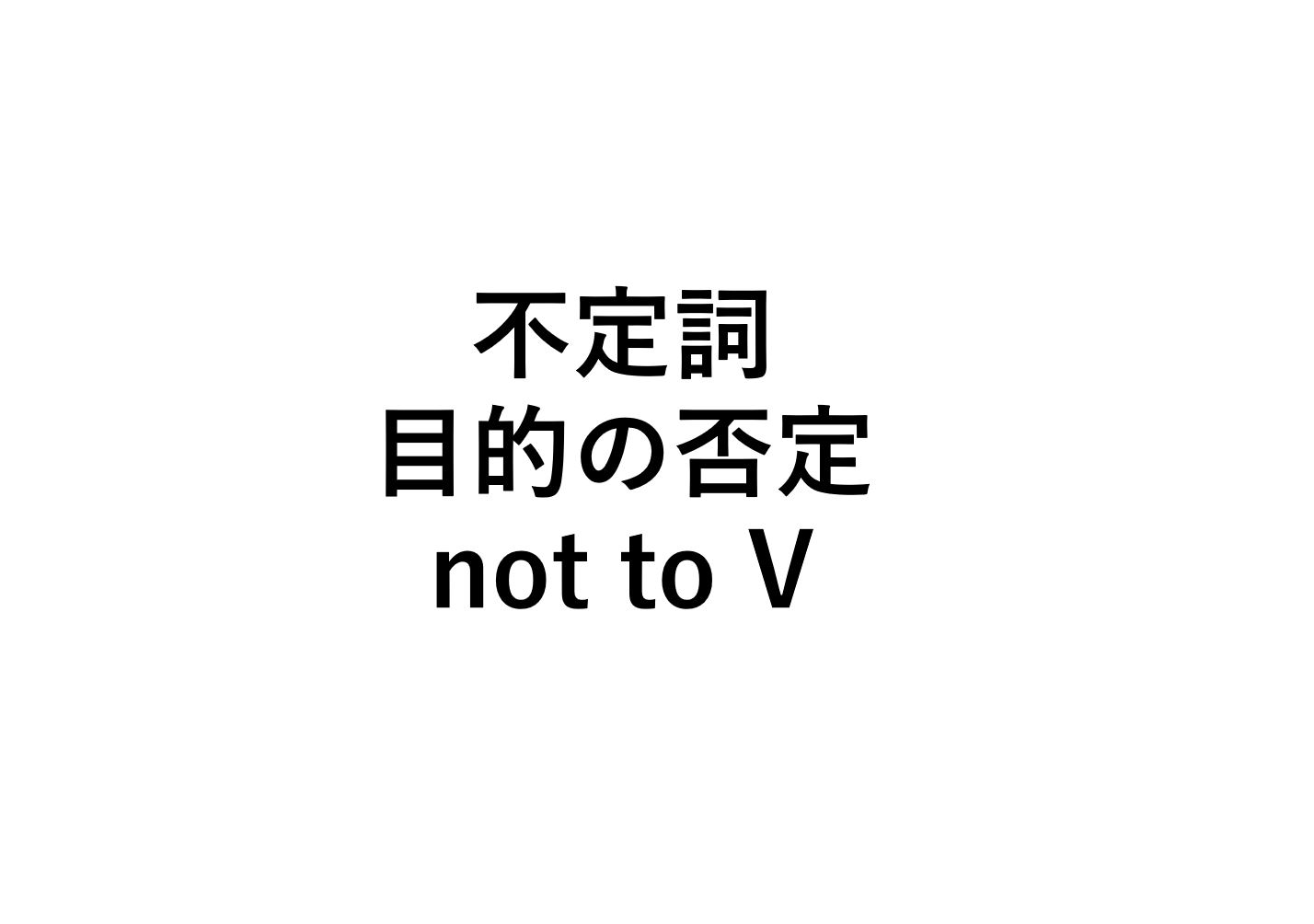
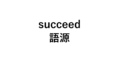
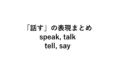
コメント