今回は関係代名詞what「人」の表現まとめです。
そのほかにも似たような慣用表現を一緒に紹介したいと思います。
サクッと確認していきましょう!
関係代名詞what「人」の表現まとめ -what S be, what we call A他
what S beで「Sの状況/Sの姿」という意味になります。what S beは関係代名詞whatのカタマリです。直訳すると「Sがある人」という意味になるのですね。
※関係代名詞whatには、「コト/モノ/人」という意味があります。
例文で見てみましょう。
I cannot imagine what he will be.
(わたしは、彼が将来どのような姿になるか想像できない)
what he will beは、「彼の将来の状況(=彼が将来あるコト)」ですね。つまり、彼が将来どんな男になるのか? サラリーマンか、プロ野球選手か、はたまたユーチューバーか。それを想像できないね、という話をしているわけです。
あと、I am what I amという歌もありますね。これは「わたしはわたし」くらいの訳になるでしょう。
時制や主語次第で様々な訳になりますが、「Sの状況/Sの姿」というコアなイメージは変わりません。参考までに下記にまとめておきます。
- what I am: 今のわたし(の姿)
- what Tokyo is: 今の東京(の状況)
- what I was: 昔のわたし(の姿)
- what I used to be: かつてのわたし(の姿)
- what Tokyo was: 昔の東京(の状況)
- what Tokyo used to be: かつての東京(の状況)
- what I will be: 将来のわたし(の姿)
- what Tokyo will be: 将来の東京(の状況)
- what I should be: あるべきわたし(の姿)
- what Tokyo should be: あるべき東京(の状況)
- what I seem to be: みかけのわたし(の姿)
- what Tokyo seems to be: みかけの東京(の状況)
上記は全て主語の入れ替えOKです。what he wasとか、what the world should beもOKということです。
一方、下記は主語をいじることの出来ない定型表現です。
- what we/you/they call A: いわゆるA(=直訳:我々/あなたたち/彼らがAと呼ぶコト)
- what is called A: いわゆるA(=直訳:Aと呼ばれているコト)
- (例)He is what we call a man of culture. (彼はいわゆる教養人というやつだ)
※ちなみに、この表現は軽蔑的な含みを持つことが多いようです。
- what be worse: さらに悪いことには(文中に挿入して使用)
- (例)We got lost, and what was worse, it began to snow. (我々は道に迷い、さらに悪いことには、雪が降り始めた)
- what is more: おまけに、そのうえ(文中に挿入して使用)
- (例)He is smart, and what is more, he is handsome. (彼は頭がよく、そのうえハンサムだ)
おわりに
いかがでしたか? 今回の表現を覚えると、こんなカッコイイことも言えます。太宰治の小説にある一節です。
He is not what he was. (彼は昔の彼ならず)
興味があったらぜひ読んでみてくださいね。(リンクはアマゾンの青空文庫なので無料です)

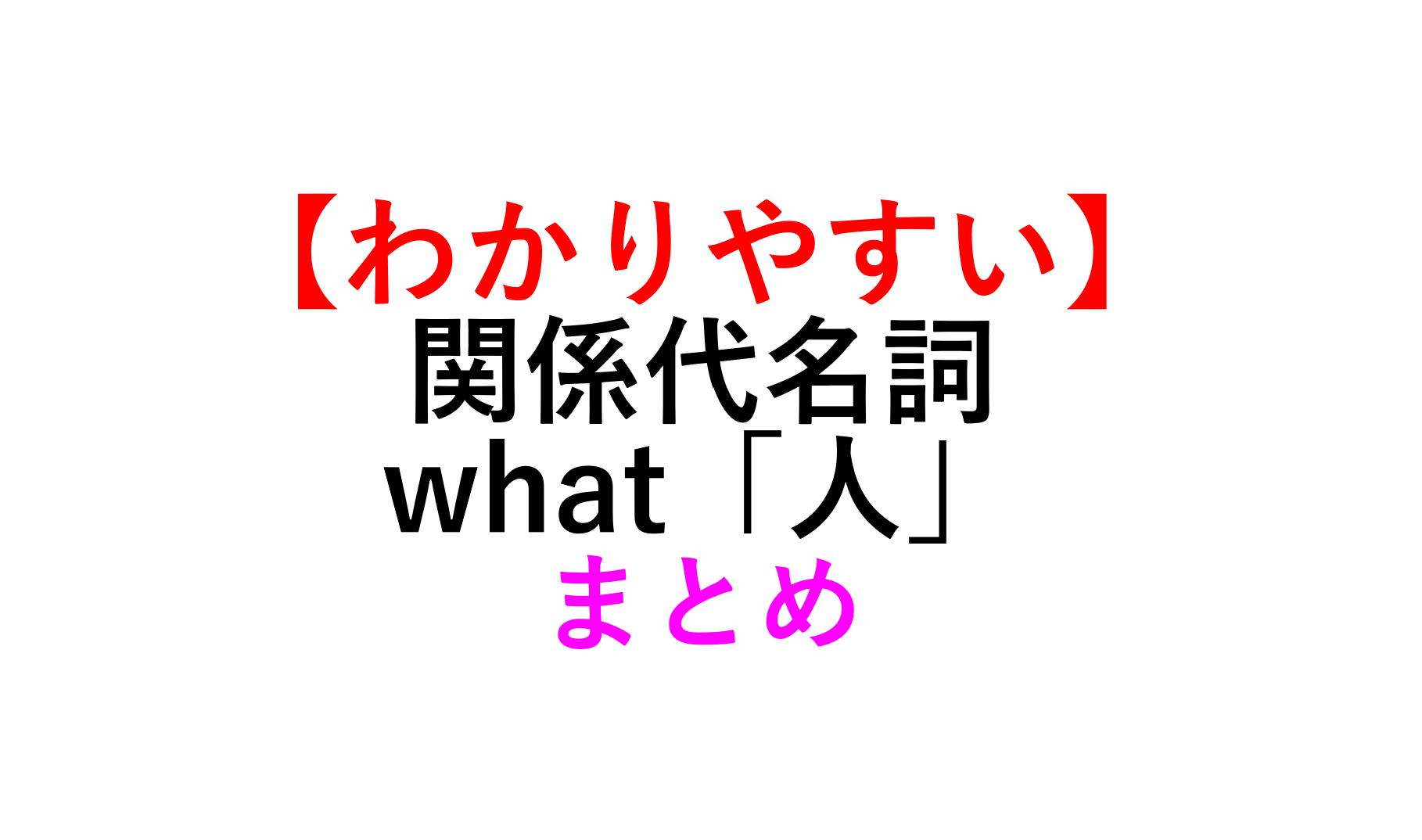

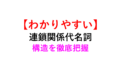
コメント