今回説明するのは「育てる」という単語の使い分けです。
grow/bring up/raiseが代表格ですが、全て使い方が異なります。
何がどのように違うのか? わかりやすく&サクッと確認していきましょう。
grow/bring up/raiseの違い -「育てる」の使い分け
「育てる」の使い分けは下記のとおりです。まずはざっと目を通して頂ければ大丈夫です。
「~を育てる」(他動詞)
- raise:人/動物/植物を育てる(動物や植物は「作物や家畜を育てる」の意味)
- bring up: 人を育てる
- grow: 植物を育てる(「作物を育てる」にも「家庭で植物を育てる」にもなる)
「育つ/成長する」(自動詞)
- grow:人/動物/植物が成長する*
* upが使われると「大人になる」を含意
使い分けを押さえる際のポイントは、
- 自動詞/他動詞か(後ろに名詞が来るか)
- 何が/何を育てるか(人? 動物や植物?)
です。
一つずつ詳しく解説していきます。
「~を育てる」(他動詞)
「~を育てる」(他動詞)から考えてきましょう。全て直後に目的語(名詞)が来ます。
raise:人/動物/植物を育てる
「raise:人/動物/植物を育てる」です。
これは万能な単語で、目的語の位置に「人/動物/植物」の何がきてもOKです。raiseの「~を上げる」というイメージが、全ての単語に対して適用されるのですね。
ただ、動物や植物の場合は「(商売として)作物や家畜を育てる」意味になりやすいです。
家で育てるような場合は、
- 植物 ⇒grow(植物を育てる)
- 動物 ⇒have/keep(動物を飼う)
を使うと良いでしょう。
例文はコチラです。目的語の人/動物/植物に注目してくださいね。
I raised Tom as a Christian.
(わたしはトムをクリスチャンとして育てた)
I raise sheep in the farm.
(わたしは農場で羊を飼育している)
I raise tomatoes in Miyazaki.
(わたしは宮崎県でトマトを育てています)
bring up: 人を育てる
「bring up: 人を育てる」です。
目的語に来て良いのは「人」だけです。「上に持ってくる」という単語のイメージが「育てる」というイメージと結びつくのですね。
例文はコチラです。人を育てている点に注目してくださいね。
He brings up his children strictly.
(彼は子供たちを厳しく育てている)
He has to bring up his family by himself.
(彼は一人で彼の家族を育てなければいけない)
He was brought up by his grandmother in Kagoshima.
(彼はおばあちゃんによって鹿児島で育てられた)
grow: 植物を育てる
「grow: 植物を育てる」です。
目的語に来て良いのは「植物」だけです。「作物を育てる」にも「家庭で植物を育てる」にもなります。
He grows vegetables in his yard.
(彼は庭で野菜を育てている)
「育つ/成長する」(自動詞)
「育つ/成長する」(自動詞)です。直後に名詞は来ません。
grow
「grow:人/動物/植物が成長する」は、自動詞として使われます。
growは「人/動物/植物」の何が育つのに使ってもOKです。なお、grow upのようにupが付く場合、「大人になる」ところまでを含意します。(「上 = 大人」にあがりきるイメージが伴うのだと考えられるのでしょう)
例文はコチラです。
The tree has grown so tall.
(その木はとても高く育った)
The lion has grown so large that we cannot keep him anymore.
(そのライオンはとても大きくなってしまったので、もはや我々はそのライオンを飼うことが出来ない)
He grew up to be a doctor.
(彼は成長して医者になった)
まとめ
いかがでしたか? 一見複雑な使い分けも、整理してみればカンタンですね!

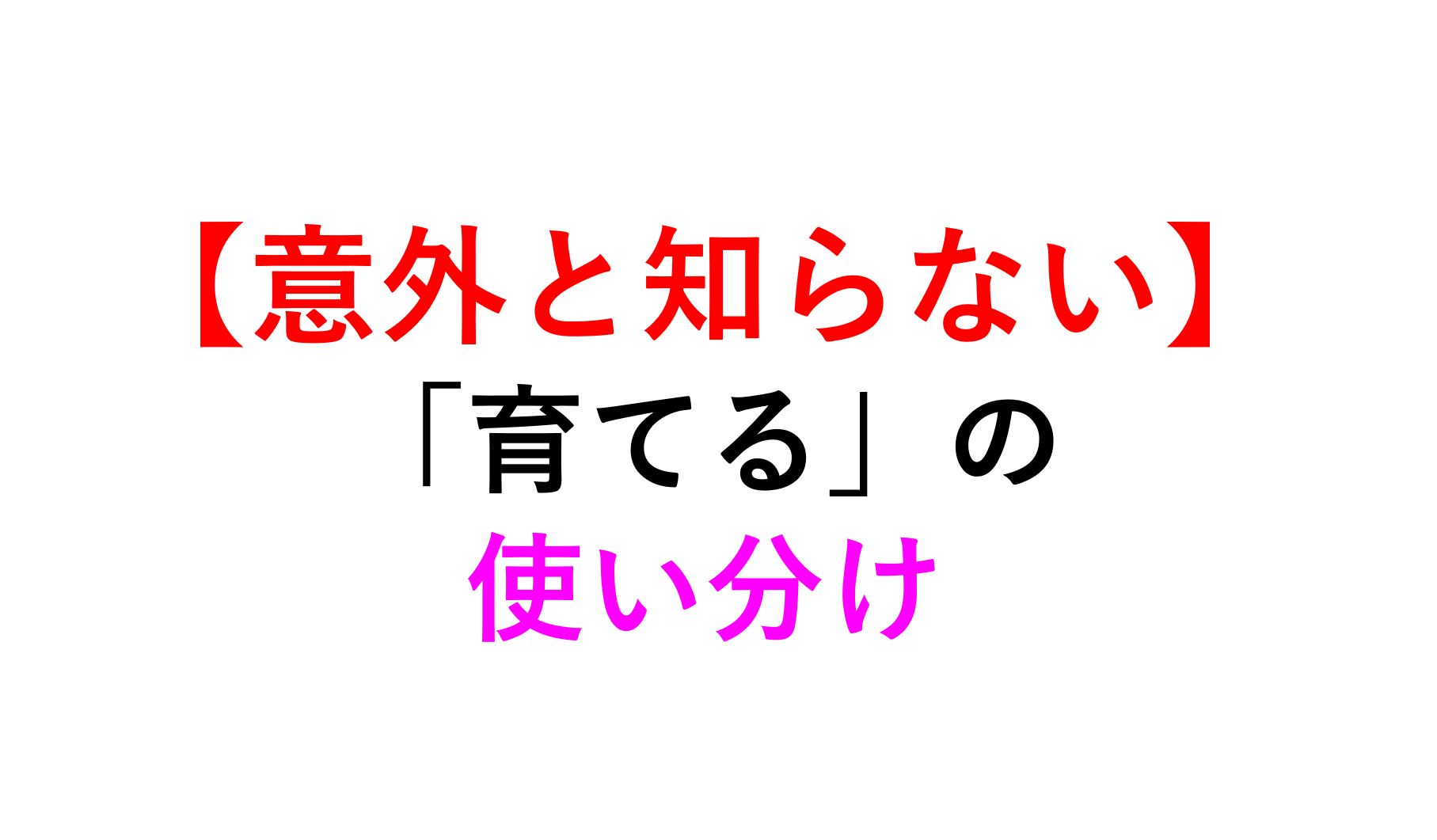
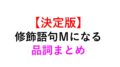
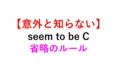
コメント