今回はhelpの使い方についてまとめてみたいと思います。
なかなかクセのある単語なので、試験でも頻出の表現です。
ただ、マスターできれば得点UP&表現の幅がグッと広がりますよ!
サクッとみていきましょう!
helpの使い方/語法まとめ
まずはhelpの使い方からまとめてみたいと思います。
下のまとめを見る際は、下記のポイントに注意してくださいね。
- 直後にとるのは「人」、「to V」、「Ving」(「物」を直後に置くのは不可!)
- 不定詞のtoは省略可
- help 人 with 物: 人の物を手伝う(物を直接目的語にとれない点に注意)
- help (to) V: Vするのを手伝う
- help O (to) V: OがVするのを手伝う*1, *2
- can’t help Ving = can’t help but V = can’t but V:~せざるを得ない *3, 4
*1 toの有無による意味の違いはあまりないです。toがない方が「直接手伝う感」が強く、toがあった方が「結果的に助けることになる感」が強い、と昔は言われていたようですが、いまはその区別も消えつつあるようです。
*2 helpが受動態で用いられる場合、必ずtoが必要になる点には要注意。
*3 helping単独で使用されれば「(食べ物の)1杯、ひと盛り」の意になるので要注意。
*4 「自分の意志で制御できず、ついついVしてしまう」という含みに注目。
例文付きで一個ずつ紹介していきます。
helpの使い方/語法の例文
helpの使い方/語法の例文は下記のとおりです。
help 人 with 物: 人の物を手伝う
まずは「help 人 with 物: 人の物を手伝う」からです。
最大のポイントは、「help 物」とはならない点です。helpは「~を助ける」という意味なので、直後に「物」を持ってくることが出来ないのですね。(「物を助ける」ってたしかにおかしいです)
そのため、「help 人 with 物」というややこしい語順になるのです。
コチラが例文です。help your homeworkはダメという点に注意です。
I helped you with your homework.
(わたしはあなたの宿題を手伝った)
help (to) V: Vするのを手伝う
次は「help (to) V: Vするのを手伝う、役立つ」です。
helpは後ろにto V (不定詞)をとることが出来ますが、なんとtoの部分だけ省略可能なのです。
コチラが例文です。下の方の例文ではtoが省略されている点に注目です。
Exercise helps to improve your health.
= Exercise helps improve your health.(運動は健康を改善するのに役立つ)
help O (to) V: OがVするのを手伝う
「help O (to) V: OがVするのを手伝う、役立つ」です。
これもやはり、toの部分が省略可である点に注意しましょう。
例文はコチラです。下の方の例文ではtoが省略されています。
He helped me to do my homework.
= He helped me do my homework.(彼は、わたしが宿題をするのを手伝った)
toがない方が「直接手伝う感」が強く、toがあった方が「結果的に助けることになる感」が強い、と昔は言われていたようですが、いまはその区別もなくなってきているようです。
なお、helpが受動態で用いられる場合、必ずtoが必要になります。なぜかというと、仮にtoがなければ、”was helped do”と動詞が三つ続く形になり、違和感があるからと考えられます。
I was helped to do my homework by him.
(私は彼によって宿題をするのを手伝ってもらった)
can’t help Ving:~せざるを得ない
最後に「can’t help Ving:~せざるを得ない」です。
これは言い換え表現もよく問われます。下記の3パターンをそれぞれ15~20回ずつ音読してくださいね。音で覚えてしまいましょう。
- can’t help Ving
- can’t help but V
- can’t but V
例文はコチラです。
I can’t help laughing.
= I can’t help but laugh.
= I can’t but laugh.(わたしは笑わざるを得ない)
「自分の意志で制御できず、ついつい笑ってしまう」という含みに注目しましょう。
たとえば、そもそも自分の意志が介在する余地がないため、下記のような英文は△です。
Because of the accident, I couldn’t help but be late for the meeting.
(事故のため、わたしは会議に遅れずにはいられなかった)
番外編 helping:(食べ物の)1杯、ひと盛り
番外編です。「helping:(食べ物の)1杯、ひと盛り」は全く異なる意味になるので要注意です。
Would you like another helping?
(お代わりはいかがですか)
まとめ
いかがでしたか? 間違いがちなhelpの用法でした。

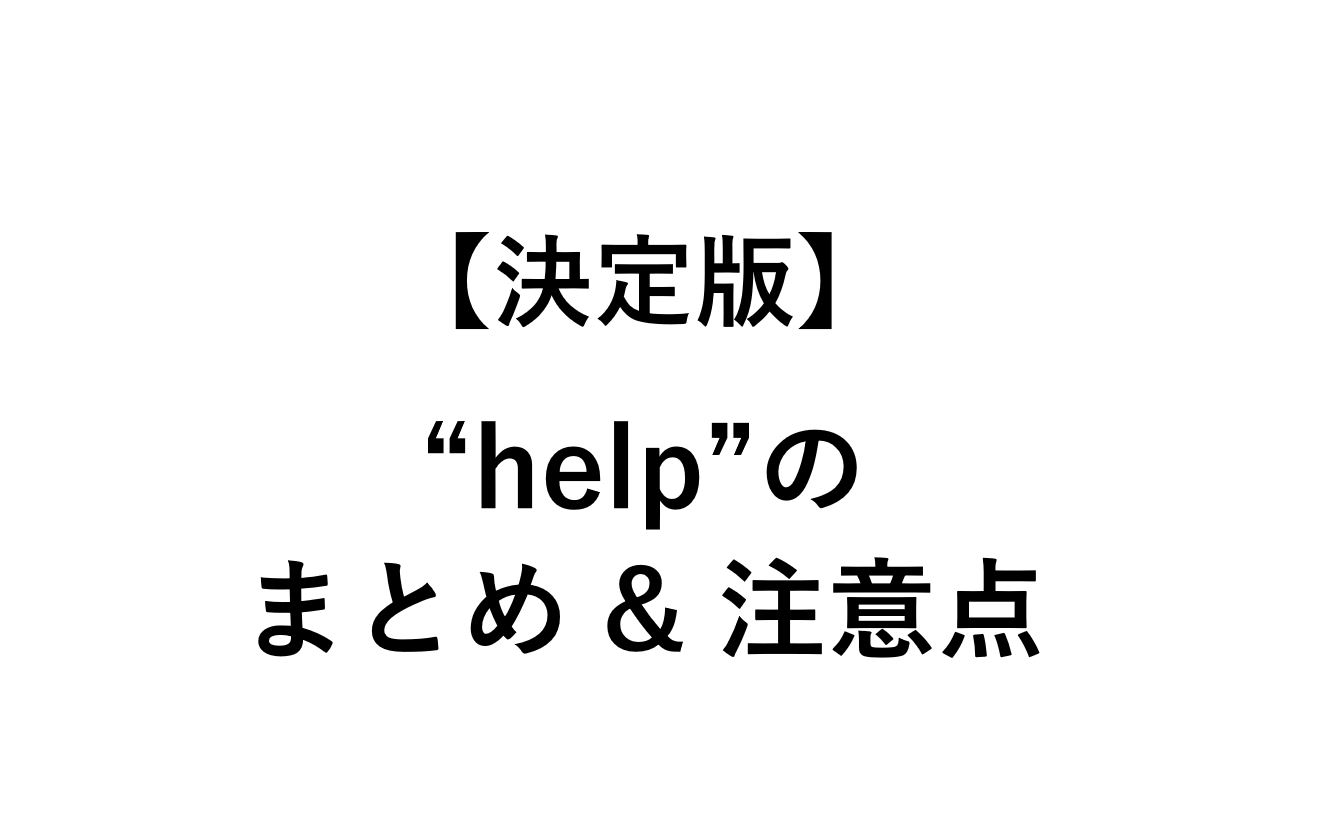
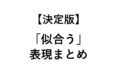

コメント
初めまして。ブログから沢山学ばせて頂いています!質問なのですが…help to V, help O to V →toが省略される場合、どういう時に省略されるのでしょうか?または省略の傾向にあるのでしょうか?英作文の時にtoを入れた方が良いのか、省略okか解らないままでいます。教えて頂けたら嬉しいです。宜しくお願い致します。
こんにちは、いつもありがとうございます!
基本的にはいつでも省略可能で、最近だと省略されることが多いようです。また、意味の違いもあまりないと考えて大丈夫です。英作文はどちらでも大丈夫です。
(toがない方が「直接手伝う感」が強く、toがあった方が「結果的に助けることになる感」が強い、と昔は言われていたようですが、いまはその区別もなくなってきているようです。ただ、ここら辺は地域や年代によっても多少ブレが存在する可能性があるので、一概にいうことは難しいですが…)
なお、helpが受動態で用いられる場合、必ずtoが必要になる点には注意してください。
He helped me (to) do my homework.
⇒I was helped to do my homework by him.
お忙しい中、早々のご返答、注意点まで有難うございました。ずっと疑問に思っていたので質問させて頂いて良かったです!先日、[as far as ],[好まれるthat]について読ませて頂いた後、ラジオ英会話でこんな英文に出会いました!
As far as I know, these are the oldest Egyptian artifacts that have been discovered.
しっかりと英語が読めた気がして感激しました。
これからも、色々な発信を楽しみにしております。