今回はcanとmayの違いをイメージ付きで理解したいと思います。
can/mayどちらも「~してもよい(許可)」という意味を持つのですが、一体どのような違いがあるのでしょう?
イメージ付きでサクッとチェックしていきましょう!
canとmay「してもよい(許可)」の違いとは
canとmay「してもよい(許可)」の違いは下記の通りです。
- can: ~してもよい(口語的)
- may: ~してもよい(上から目線、カタい、公的な許可)
canは「できる⇒してもよい」という発想です。
例えば、日本語でも「できる」は「してもよい」の意味になることがありますよね。しかも、結構カジュアルな文脈で使われます。
「この本、借りられますか (=借りてもよいですか)?」
「大丈夫ですよ」
一方のmayは「上から目線の許可」です。
mayには「かもしれない」という意味もありますが、やはりこれも上から目線で「その可能性を妨げるものは何もない」とその道を開いてやっているイメージです。
上から目線なので、「カタい」イメージになりますし、文脈次第では「公的な許可を与える」イメージにもつながります。
can/mayの例文
上記を踏まえたうえでcan/mayの例文を見ていきましょう。
You can read this book.
(この本を読んでもよい)
You may read this book.
(この本を読んでもよろしい)
You can smoke here.
(ここで煙草を吸ってもよい)
You may smoke here.
(ここで煙草を吸ってもよろしい)
mayの方は堅苦しい感じを与えるのと同時に、文脈次第では「公的な許可」の意味にもなります。
たとえば、
- You can smoke here.
は話し手が主観的に「煙草吸ってもいいよ」と言っているのに対し、
- You may smoke here.
は法律や規則などが「煙草を吸うことを許可している」感じがします。
(なので、規則を示す文書ではmayが使用されます)
また、
- May I help you? (いらっしゃいませ)
は定型表現として習った方も多いと思います。
これは「わたしがあなたのお手伝いしてもよろしいでしょうか =いらっしゃいませ」という発想の文です。お客さんに対する発言なので、カタイイメージのmayが使われているのですね。
おわりに
いかがでしたか?
このように、canとmayは細かいニュアンスが異なるのですね。学校では「ほぼ同じ」と教えられ、その違いが問われることはあまりないですが、実際の運用は結構違います。
最後にまとめを再掲しておきますので、ザっと目を通してみてください。
- can: ~してもよい(口語的)
- may: ~してもよい(上から目線、カタい、公的な許可)

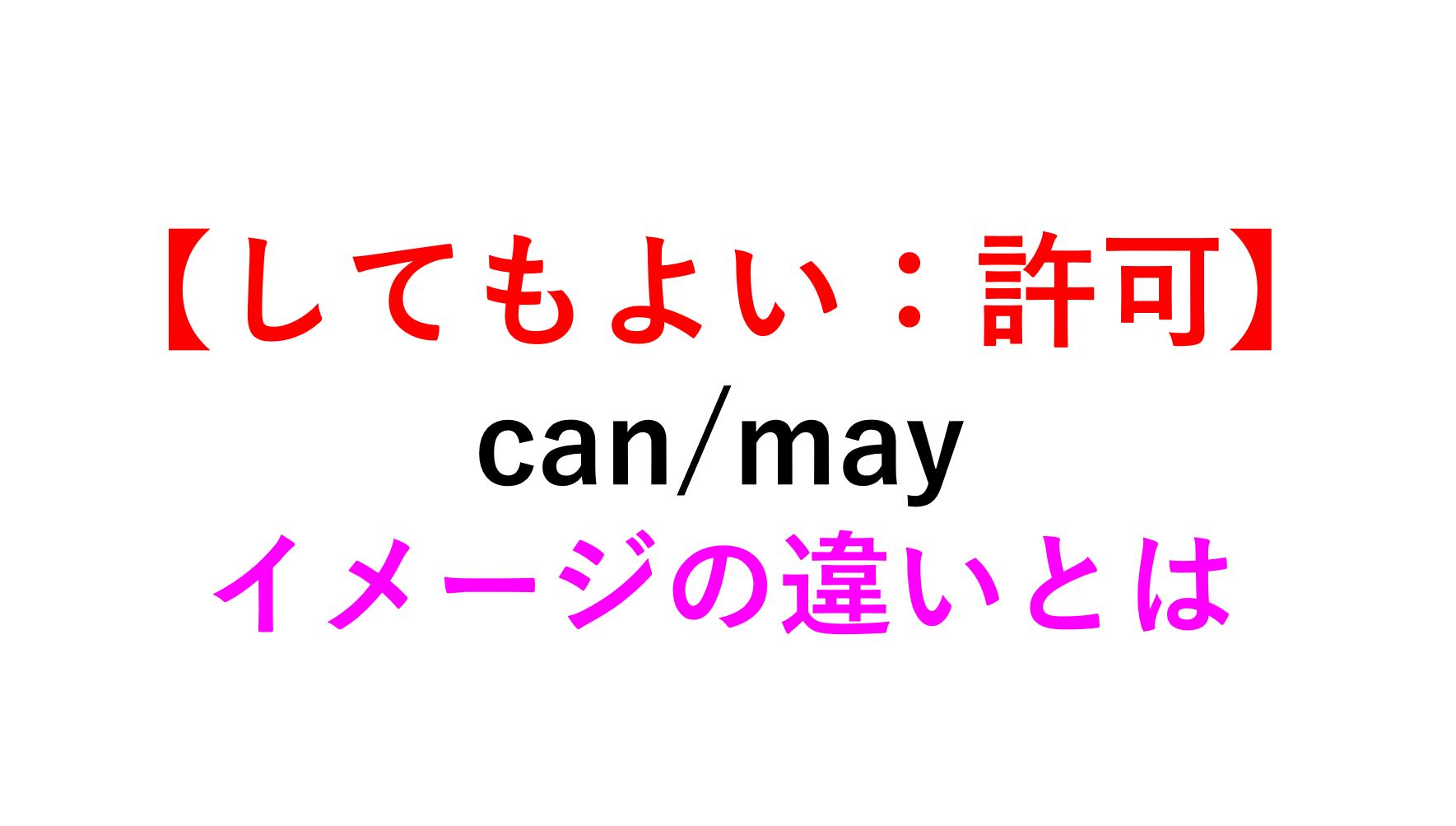

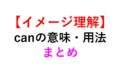
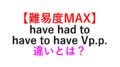
コメント
[…] 【学校では教えない】canとmayの違いをイメージで理解【~してもよい:許可】 […]