突然ですが、asやbut, thanが関係代名詞になることがあるって知っていました?

知らなかった…
as, but, thanのように、「一見すると関係代名詞っぽくはないモノ」を疑似関係代名詞と呼びます。
疑似関係代名詞としてのbutはややマイナーな印象ですが、asやthanは文章を読んでいても結構出くわす表現です。
今回はas, but, thanを順番に説明していきます!(分量的にはasの説明が多くなると思います)
疑似関係代名詞as, but, thanの意味・用法まとめ
まずは全体像から示します。今回の記事では下記の内容を説明していきます。
<as>
- 非制限用法として使用(whichとの違いは、「①asのカタマリは先行詞より前に来ることも可能」「②as内で否定語を使うのはダメ、which内で否定語を使うのはOK」「③asが主格になる時はbe動詞やseem、appearなどしか使えない」という点)
よく使われる定型表現は下記の通り
- such A as B: BのようなA
- the same A as B: Bと同じA
- as A as B: Bと同じA
- as is often the case with A: Aにはよくあることだが
- as is usual with A: Aにはよくあることだが
- as is evident from A: Aから明らかなように
- as so often happens: よくあることだが
- as might have been expected: 期待通りに、さすがに
<but>
- ~but…で、「…でない~」という意味
- butをthat…notで書き換えるとわかりやすい
<than>
- ~than…で「…以上の~」という意味
以下、個別の表現を見ていきましょう。
疑似関係代名詞as
まずはasからいきましょう。疑似関係代名詞asにはいくつかパターンがあるので、パターン別に見ていきたいと思います。
非制限用法のパターン
非制限用法のasです。前の文を先行詞にします。 ~, as…で「…なように、~だ/…ではあるが~だ」と訳すのが基本です。
なお、非制限用法とは、直前にカンマが置かれている用法のことです。詳しくは下記記事にありますので、よろしければ参考にしてみてください。5分程度でサクッと読めます。
参考記事:非制限用法とは? 制限用法との違い
例文はコチラ。先行詞は前の文の内容です。
He is very lazy, as his work shows.
= As his work shows, he is very lazy.
= He is very lazy, which his work shows.
(彼の仕事ぶりが示しているように、彼はとても怠惰だ)
一番上の例文を見てください。これは2つの文に分解することが出来ます。asが指している内容(前の文の内容)に注目です。
He is very lazy, as his work shows.
- He is very lazy. (彼はとても怠惰だ)
- his work show as (=He is very crazy). (彼の仕事ぶりがそのこと(=彼はとても怠惰だ)を示している)
whichにも同じ用法がありますが、whichとの違いは、asのカタマリは先行詞より前に来ることも可能な点です。
(註:他には、「①as内で否定語を使うのはダメ、which内で否定語を使うのはOK」、「②asが主格になる時はbe動詞やseemなどしか使えない」という違いもあります)
such A as Bのパターン
such A as Bの形で、asが関係代名詞的に使われることがあります。先行詞Aを、as Bのカタマリが修飾するように訳します。「BのようなA」という訳が基本になります。
例文はコチラ。
This is such a book as can be easily understood.
(これは、簡単に理解出来るような本です)
2つに分解すると下記の通り。
This is such a book as can be easily understood.
- This is such a book. (これはそのような本である)
- as (= a book) can be understood. (その本はカンタンに理解できる)
なお、such A as Bは、関係代名詞ではないパターンもあるので一応注意です。訳は同じく「BのようなA」
関係代名詞such A as Bとの違いは、Bの部分に名詞が来るコトです。(関係代名詞のパターンだと文が来てましたね)
I don’t know such animals as these.
(これらのような動物を知らない)
the same A as Bのパターン
the same A as Bの形で、asが関係代名詞的に使われることがあります。
such A as Bと似ていますね。先行詞Aを、as Bのカタマリが修飾するように訳します。「Bと同じA」という訳が基本になります。theを忘れないでくださいね。(「同じモノ」なので、theを使って「それ!」と特定するようなイメージです)
例文はコチラ。
This is the same book as he has.
(これは、彼が持っているのと同じ本です)
2つに分解すると下記の通り。
This is the same book as he has.
- This is the same book. (これは同じ本である)
- he has as (= the same book). (彼は同じ本を持っている)
なお、前半部分と後半部分で同じ動詞が使われるときは、後半部分の動詞が省略されることもあります。
I have the same book as he (has).
(わたしは、彼が持っているのと同じ本を持っています)
as A as Bのパターン
as A as Bの形で、asが関係代名詞的に使われることがあります。先行詞Aを、as Bのカタマリが修飾するように訳します。「Bと同じA」という訳が基本になります。
例文はコチラ。
He is given as much food as he can barely live on.
(彼は、かろうじて生きているだけの食料を与えられている
= 直訳:彼は、彼がかろうじて生きていけるのと同じ量の食料を与えられている)
2つに分解すると下記の通り。
He is given as much food as he can barely live on.
- He is given as much food. (彼はその量の食料を与えられている)
- He can barely live on as (= much food). (彼はその量の食糧でかろうじて生きていける)
なお、as A as Bは、関係代名詞ではなく、比較級のパターンもあるので一応注意です。訳は「Bと同じくらいA」
関係代名詞as A as Bとの違いは、Bの部分が完全な文を前提としているコトです。
He is as tall as I.
= He is as tall as I am tall. (省略ナシ。前提としている文)
- He is as tall. (彼は同じくらい背が高い)
- I am tall. (わたしは背が高い)
(かれは私と同じくらい身長が高い)
関係代名詞のパターンだと、Bの部分にasを埋めないと完全な文にならないんです。ただ、比較級のパターンだとBの部分にasを埋めなくても完全な文になります。今回なら、I am tallというのは、asなしでも完全な文として成り立っていますね。これは、後ろの方のasが接続詞 (andとかと同じ)として使用されているからです。
その他定型表現のパターン
その他定型表現がいくつかあるので、まとめて紹介します。ここでのasは、全て非制限用法的に使われています。
- as is often the case with A: Aにはよくあることだが
- as is usual with A: Aにはよくあることだが
- as is evident from A: Aから明らかなように
- as so often happens: よくあることだが
- as might have been expected: 期待通りに、さすがに
いくつか例文を示しておきます。
非制限用法なので、前の文の内容を先行詞にしています。順番は入れ替え可能です。
He didn’t listen to me, as is often the case with him.
= As is often the case with him, he didn’t listen to me.
(彼にはよくあることだが、彼はわたしの話に耳を傾けなかった)
As is usual with him, he didn’t listen to me.
(彼にはよくあることだが、彼はわたしの話に耳を傾けなかった)
As is evident from these examples, he is lazy.
(これらの例から明らかなように、彼は怠惰だ)
疑似関係代名詞but
次は疑似関係代名詞butです。固い表現で、日常会話で使うことはほぼない気がします。先行詞が否定的な語であるとき、butが関係代名詞的に使われることがあります。
「~but…: …でない~」と訳すのが基本です。
「= that…not」と考えるとわかりやすいです。
コチラの例文では、先行詞nobodyを、but has moneyという関係代名詞のカタマリが修飾しています。
There is nobody but has money.
= There is nobody that does not have money.
(お金を持っていない人は一人もいない)
2つに分解すると下記の通りです。
There is nobody but has money.
- There is nobody. (だれもいない)
- nobody (=but) does not have money. (だれもお金を持っていないわけではない)
疑似関係代名詞than
最後は疑似関係代名詞thanです。~than…で「…以上の~」と訳すのが基本です。比較表現(moreや-erなど)と一緒に使われます。
There is more water than is needed.
(必要以上の水がある)
2つの文に分解すると下記のとおりです。
There is more water than is needed.
- There is more water. (必要以上の水がある)
- Water (=than) is needed. (水が必要である)
まとめ
いかがでしたか? 最後に今回の内容を改めてまとめておきます。
<as>
- 非制限用法として使用(whichとの違いは、「①asのカタマリは先行詞より前に来ることも可能」「②as内で否定語を使うのはダメ、which内で否定語を使うのはOK」「③asが主格になる時はbe動詞やseem、appearなどしか使えない」という点)
よく使われる定型表現は下記の通り
- such A as B: BのようなA
- the same A as B: Bと同じA
- as A as B: Bと同じA
- as is often the case with A: Aにはよくあることだが
- as is usual with A: Aにはよくあることだが
- as is evident from A: Aから明らかなように
- as so often happens: よくあることだが
- as might have been expected: 期待通りに、さすがに
<but>
- ~but…で、「…でない~」という意味
- butをthat…notで書き換えるとわかりやすい
<than>
- ~than…で「…以上の~」という意味

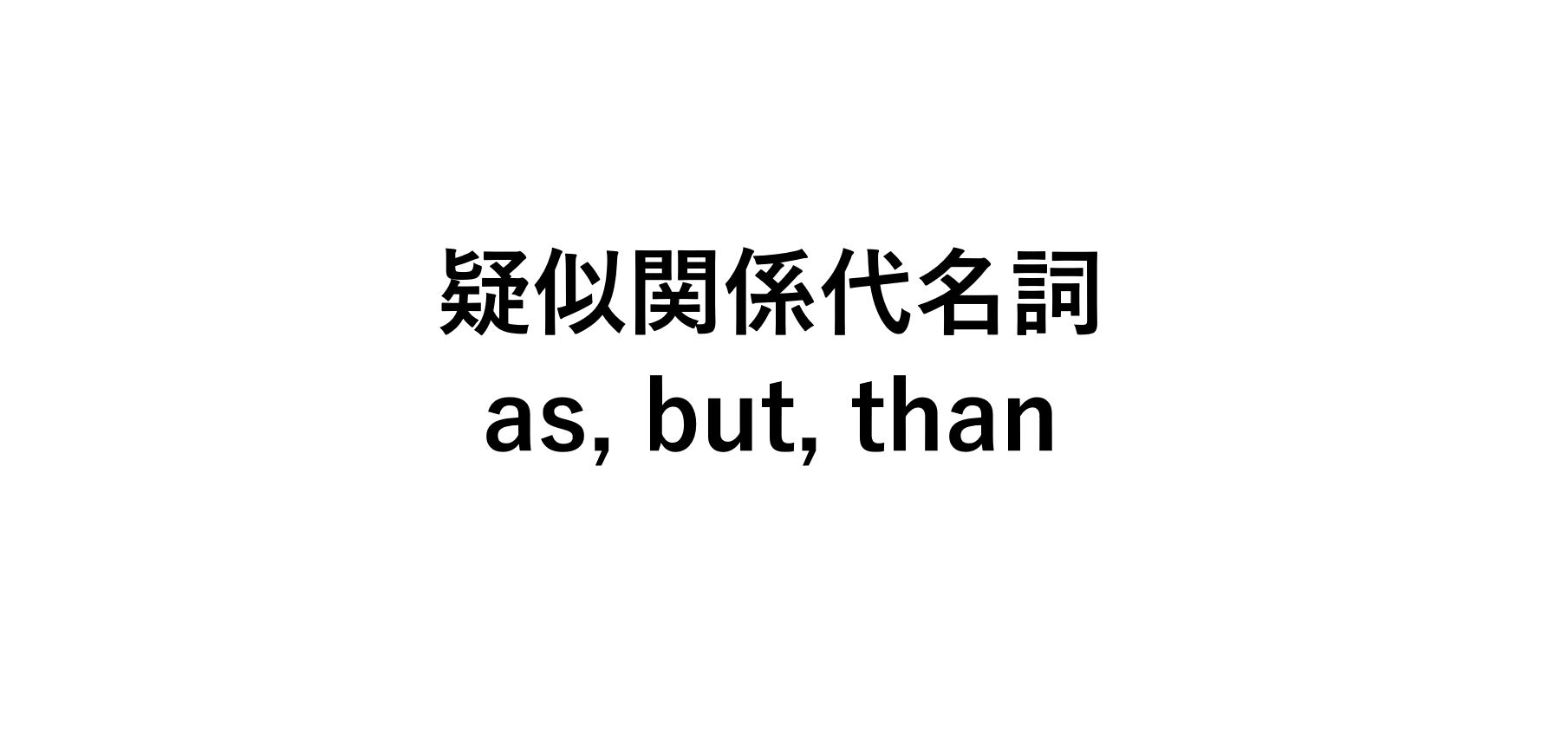

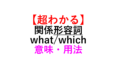
コメント
[…] 【関係代名詞as, but, than】疑似関係代名詞とは? […]