今回はnotのない否定表現をまとめてみたいと思います。
一見否定的な意味には見えないにもかかわらず、否定的な意味を持ちうる表現です。
大学受験をはじめとした試験はもちろんのこと、英文で読書をしていてもよくみかける表現ばかりです。これを機会に、一気に確認してしまいましょう!
notを使わない否定表現まとめ
まずは全体像から。notのない否定表現まとめは下記の通りです。
- above 名詞:~ではない
- beyond 名詞:~ではない(標準を超えているイメージ)
- the last 名詞 that (to V): 決して~ではない名詞
- never V without A, cannot V without A: Vすると必ずAする(≒AなしにVはしない)
- nothing but A: Aにすぎない
- anything but A: 決してAではない、少しもAではない (=far from A)
- have no choice but to V: Vすること以外に選択肢がない
- in vain: むだに、むなしく
- have yet to: まだ~していない(yetまだ+have toしなければいけない)
- remain to be~:まだ~されていない
- know better than to~:~するほど馬鹿ではない

これだけみてもわからない…
大丈夫です。
例文と一緒に、個別に確認していきましょう!
notを使わない否定表現の例文
notを使わない否定表現の例文です。
above 名詞:~ではない
まずは「above 名詞:~ではない」からです。
aboveには「はるか上」というニュアンスが含まれています。
※above/below/over/underの意味の違いを知りたい方はコチラの記事をぜひお読みください
【本質から理解!】前置詞over, under / above, belowの違い
つまり、「はるか上にある」⇒「かけ離れている」⇒「~ではない」という発想ですね。
コチラが例文です。
His conduct was above suspicion.
(彼の行動は疑惑の余地がなかった)
She is above telling a lie.
(彼女は決してウソをつかない)
beyond 名詞:~ではない
「beyond 名詞:~ではない」です。
beyondには、ある境界を超えた向こう側というニュアンスがあります。
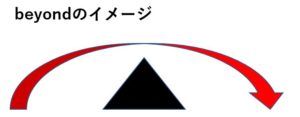
※beyondの詳しい意味はコチラの記事にまとめてあります。
このようなbeyondのイメージと結びつき、「beyond 名詞:~ではない」は、
「標準を超えていて支配、期待、比較などが追い付かない」というニュアンスで使用されることが多いです。
コチラが例文です。文脈次第では、ムリに否定として訳さなくてOKです。
His idea is beyond the reach of my comprehension.
(彼の考えは私の理解の範囲を超えている)
The task is beyond me.
(その作業はわたしの能力を超えている)
the last 名詞 that (to V): 決して~ではない
「the last 名詞 S V (to V): 決して~ではない」です。
次のいずれかの形で使われます。
- the last 名詞 that ~
- the last 名詞 to V
that~は関係代名詞、
to Vは不定詞の形容詞のカタマリです。
つまり、どちらも直前の名詞を修飾している(説明している)わけです。
直訳すると、「~する最後の名詞」というイメージです。
例文と一緒に、もう少し詳しく見てみましょう。太字部分の名詞を、下線部のカタマリが修飾しています。
He is the last person to do such a thing.
(彼は決してそんなことはしない)
直訳: 彼は、そんなことをする最後の人間だ
この例文を直訳すると「彼は、そのようなことをする最後の人間だ」です。
「そのようなことをしそうな順」に知っている人間を全員一列に並べていき、その最後にくるのが彼…つまり、「彼はそのようなことを一番しなさそうだ」ということになります。
もう一つくらい例文を見ておきましょう。こちらは後ろに関係代名詞のカタマリが来ているパターンです。
She is the last person I want to see.
(彼女には、決して会いたくない)
直訳: 彼女は、わたしが会いたい最後の人間だ
never V without A, cannot V without A: Vすると必ずAする
「never V without A, cannot V without A: Vすると必ずAする」です。
これも直訳で考えるとわかりやすいです。
「AなしにVはしない」というのが直訳なので、「Vすると必ずAする」という和訳になるわけです。
コチラが例文です。
She never goes out without losing her umbrella.
(彼女は外出すると必ず傘をなくす)
直訳:彼女は、傘をなくすことなしに決して外出しない
You cannot commit a crime without being punished.
(罪を犯せば必ず罰せられる)
直訳:あなた (註:一般論としての「あなた」)は、罰せられることなしに罪を犯すことは出来ない
nothing but A: Aにすぎない / anything but A: 少しもAではない
この二つは一緒に見ていきましょう。
- 「nothing but A: Aにすぎない」
- 「 anything but A: 少しもAではない (= far from A)」
まず、「but: ~以外」という意味があることに注目しましょう。
そのうえで、例文を直訳しながら考えていきます。
まずはnothing butから。nothingには「なにもない」という意味があるので、直訳すると下記の通りになります。
He is nothing but a hero.
(彼はなんでもない。英雄以外の
⇒彼はただの英雄だ)
次にanything butです。anythingには「なんでも」という意味があるので、直訳すると下記の通りになります。
He is anything but a hero.
(彼は全てのモノだ。英雄以外の
⇒彼は決して英雄ではない)
世の中にはスポーツマン、ジェントルマン、リーダータイプの人間…色々いるわけですが、かなりテキトーに、彼は全部に当てはまると言っているわけです。
ただ、色々当てはまるんだけど、その中から英雄の可能性は除くよ、というのが今回の文です。
色々当てはまる中からわざわざ除くくらいだから相当です。彼は、決して英雄などではないというわけです。
なお、anything but Aはfar from Aなどで言い換えることが出来ます。
「Aから遠い」⇒「少しもAではない、決してAではない」という発想ですね。
He is far from a hero.
(彼は英雄などではない)
have no choice but to V: Vすること以外に選択肢がない
「have no choice but to V: Vすること以外に選択肢がない」です。
ここでも「but: ~以外」の意味で使われていますね。
コチラが例文です。
She had no choice but to do it.
(彼女はそれをするほか、選択肢がなかった)
in vain: むだに、むなしく
「in vain: むだに、むなしく」です。
「vain: 空虚な」という意味があるのですね。
コチラが例文です。in vainは文中や文末に置かれることが多いです(文末の場合はbutを伴うこともあります)。
I tried in vain to beat him.
= I tried to beat him (,but) in vain.
(わたしは彼を倒そうとしたが無駄に終わった)
All his labor was in vain.
(彼の労働は全て無駄になった)
have yet to: まだ~していない
「have yet to: まだ~していない」です。
これは、
- have to~: ~しなければいけない
- yet: まだ
に分解して考えましょう。
つまり、「まだ~しなければいけない」⇒「まだ~していない」ということですね。
こちらが例文です。
We have yet to receive their reply.
(わたしたちは、まだ返事を受け取っていない)
remain to be~:まだ~されていない
「remain to be~:まだ~されていない」です。
remainには「~のままである、とどまる」という意味があることを考えると、この表現も理解しやすいですね。
コチラが例文です。
This problem remains to be solved.
(この問題はまだ解かれていない)
know better than to~:~するほど馬鹿ではない
最後に「know better than to~:~するほど馬鹿ではない」です。
次のように分解するとわかりやすいですね。
- know better: よりよく知っている
- than: ~よりも
- to V: to Vする
つまり、「to Vするよりも、よりよく知っている」⇒「to Vするほど馬鹿ではない」というコトですね。
コチラが例文です。
He knows better than to do such things.
(彼はそのようなことをするほど馬鹿ではない)
まとめ
いかがでしたか? 最後に改めてまとめを載せておきます。
- above 名詞:~ではない
- beyond 名詞:~ではない(標準を超えているイメージ)
- the last 名詞 that (to V): 決して~ではない名詞
- never V without A, cannot V without A: Vすると必ずAする(≒AなしにVはしない)
- nothing but A: Aにすぎない
- anything but A: 決してAではない、少しもAではない (=far from A)
- have no choice but to V: Vすること以外に選択肢がない
- in vain: むだに、むなしく
- have yet to: まだ~していない(yetまだ+have toしなければいけない)
- remain to be~:まだ~されていない
- know better than to~:~するほど馬鹿ではない

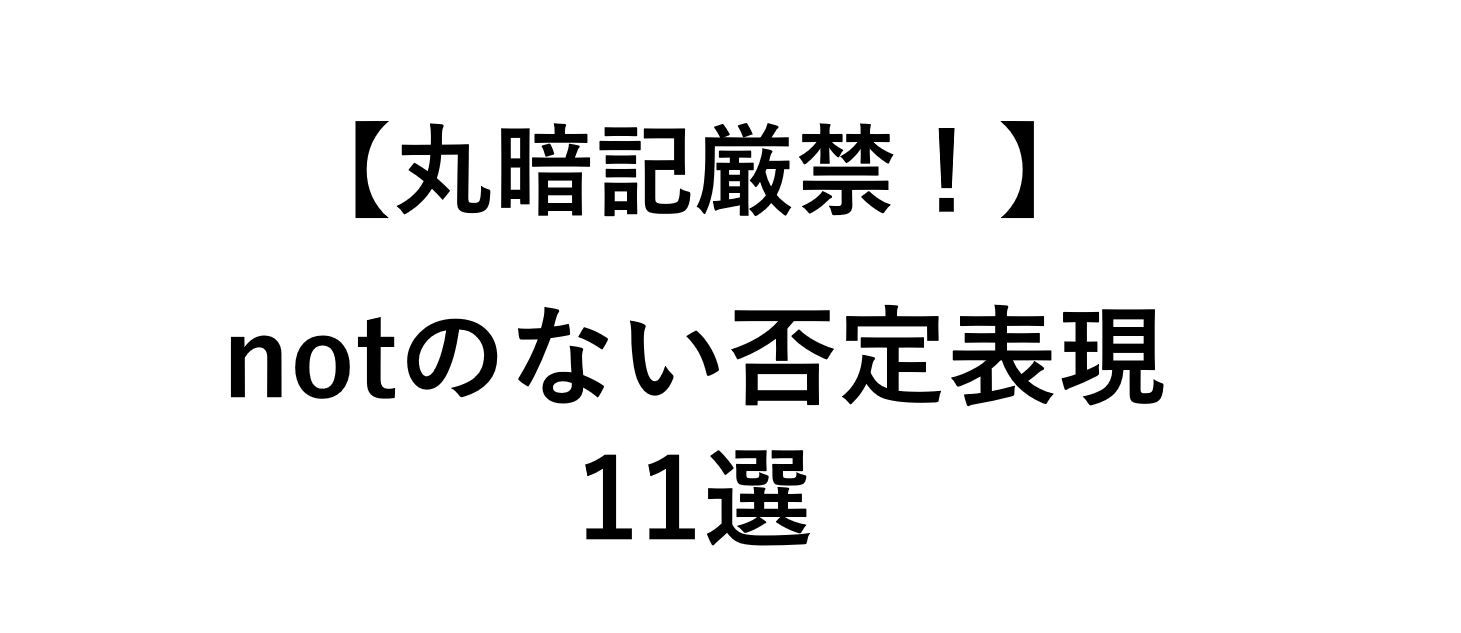
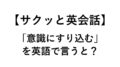
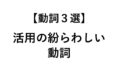
コメント